こんにちは!日々仕事に追われながらも「もっとうまくやれたらな…」なんて思うこと、ありませんか?私もそんな一人です。でも最近、仕事の悩みを軽くする方法に気づいたんです。
それは「主体性」と「量」を軸に考えること。
今回は、私が感じた5つの視点をブログ風にシェアします。少し長いけど、最後まで読んでくれたら何かヒントが見つかるかも!
1. 主体的に働くって、自分の天気を持つこと
仕事で落ち込むときって、天気みたいに周りの状況に振り回されてませんか?上司の機嫌が悪いとか、クライアントの反応がイマイチとか。でもね、主体的な人って「自分の中に自分の天気」を持ってるんです。雨が降ろうが陽が照ろうが関係ない。自分の価値観で動くからブレないんですよ。
例えば、私の価値観は「質の高い仕事をする」こと。これを軸にすれば、天気が悪くても仕事に集中できる。逆に「感情は自由だ!」なんて言ってプロ意識を放棄する上司っていますよね。そういう人は部下から見放されて、チームのモチベーションまで下げちゃう。主体性が大事な証拠です。
人脈づくりも同じ。焦って無理に繋がろうとしなくても、目の前の仕事や人に全力で向き合えば、自然と信頼が生まれるんです。主体性って、自分のペースで進むためのコンパスみたいなもの。悩みが減るし、成果も上がる。一石二鳥ですよ!
2. 質の高い仕事は「量」からしか生まれない
「仕事の質を上げたいけど、どうすれば…?」って悩むこと、ありますよね。私も最初はそうでした。でも気づいたんです。質って、いきなり上がるものじゃない。量をこなして、試行錯誤を繰り返す中で磨かれるものなんです。
考えてみてください。プロと素人の差ってどこにあると思いますか?それは「量」。フィードバックをもらった量、地雷を踏んだ量、試行錯誤した量。これが積み重なると、精度が上がって「質の高い仕事」ができるようになるんです。新しく始めた仕事で最初からゴールが見える人なんていないですよね。受験も就活も子育てだってそう。悩みながら手を動かし続けた人が、最後に笑うんです。
先輩の失敗談を聞くのもおすすめ。経験に裏打ちされた話は現場で役立つし、「量」の大切さを教えてくれます。質に悩むなら、まず量を恐れず動いてみること。それが成長への近道です。
3. 他者や会社に期待しすぎない生き方
仕事でイライラする時って、他人や会社に期待しすぎてませんか?私も昔は「上司がこうしてくれれば…」「会社がもっとサポートしてくれたら…」なんて思ってました。でも、それって自分で勝手に期待を膨らませて、裏切られた気分になってるだけなんですよね。
例えば、同僚の価値観が自分と違って反発したくなる時。でも堪えて観察すると、新しい視点が得られるんです。私は昭和世代だけど、会社に依存せず「学びの場」として捉えてます。コロナ禍で働き方が変わったのも、プライベートとのバランスを取る良いきっかけだったし。
一般論でアドバイスしてくる人の話は、ニコニコ聞き流すのが吉。経験が伴ってない言葉は現場では通用しないし、真に受けて頑張りすぎると心が疲れちゃう。先輩の失敗談の方が100倍参考になります。他人に期待せず、自分で学びを見つける。これがストレスを減らすコツです。
4. 過去を悔やむより、今の姿勢をコントロール
過去のミスを引きずって「もっとこうしてれば…」って後悔すること、ありますよね。私も多忙な日々で失望したり期待を裏切られたりして落ち込む時があります。でもよく考えると、外面だけ見て勝手に過剰な期待をしてただけだったりするんです。
主体的であるためには、過去を悔やむより「今どう反応するか」に集中するのが大事。過去は「影響の輪の外」にあって、コントロールできない。人生には3つの価値観があるって言うんですよ。「経験」(起こること)、「創造」(自分で作るもの)、そして「姿勢」。特に「姿勢」が大事。傷つくのは出来事じゃなくて、それに対する自分の反応なんです。
例えば、失敗したプロジェクトを悔やむより「次はどうするか」を考える方が建設的。過去は呼び戻せないけど、今の選択は自分で決められる。そこに主体性の強さがあると思います。
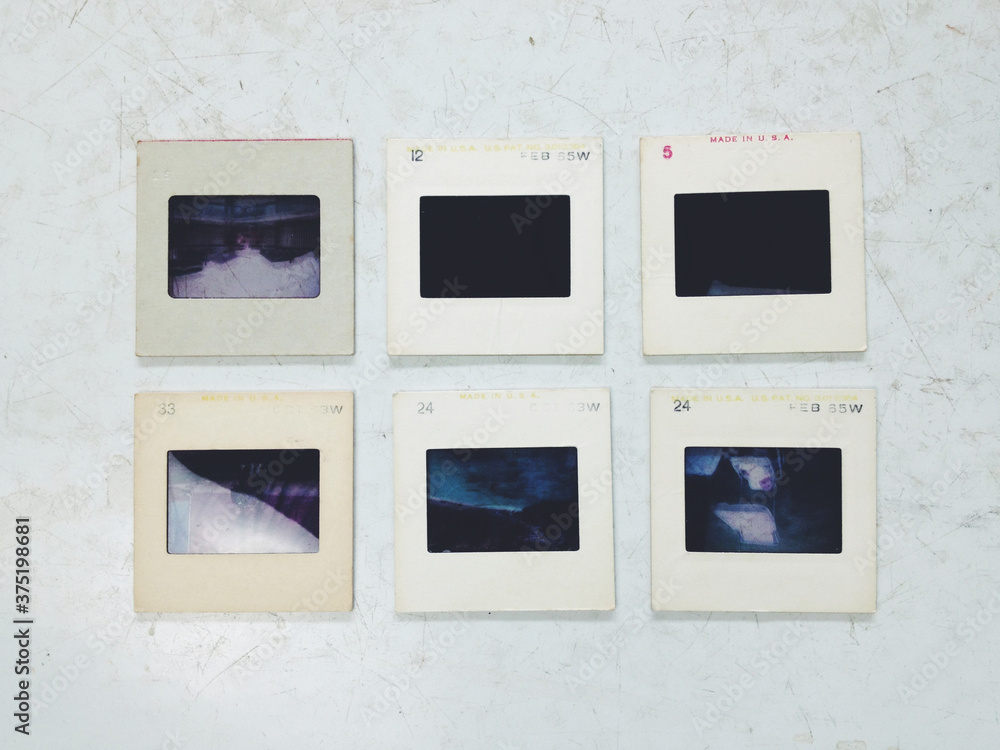
5. 相手を理解する努力は必ず返ってくる
最後に、人間関係の話。仕事って一人じゃできないですよね。人は誰でも「わかってもらいたい」と思ってる。だから、相手を理解する努力って絶対に無駄にならないんです。
価値観が違う人と向き合うのは大変だけど、観察すれば学ぶことがたくさんある。長い時間をかけて相手を知ると、信頼が生まれて仕事がスムーズに進む。逆に感情的な態度で関係を壊す上司は、その対極にいる典型例です。
私も忙しい中で失望することもあるけど、内面を知ることで「次に活かそう」と思えるようになりました。理解への投資は、信頼や成果となって返ってくる。仕事の悩みが減るし、人間関係も強くなる。最高のWin-Winですよね。
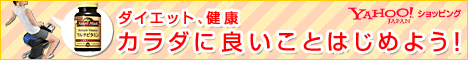



コメント